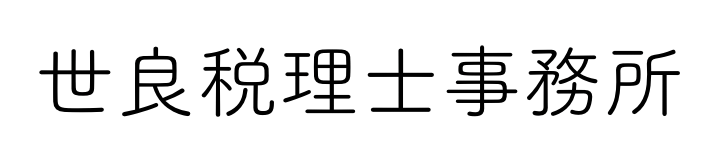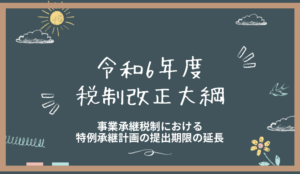贈与税の時効
こっそり贈与してもバレないと思ってませんか?
ドキッとされた方は挙手してください(笑)。
悪意を持って過去に贈与した事実を隠蔽しているのではなくて、例えば自分の乗っていたベンツが要らなくなったので息子にあげたみたいに、「家族なんだから贈与なんて関係ないでしょ」といった勘違いで申告もせずそのままにしている例はたくさんあります。
後日、「それは贈与だよ」と聞かされ、不安で何も手につかない、なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この贈与税ですが、その他の税金と同じく、「時効」があります。一般的には6年、悪質な場合は7年と決められています。その他の一般的な税金に係る時効は5年と定められていますが、贈与税については例外的に時効までの期間が長くなっています。
時効と表現していますが、正確には税務署長が贈与税について更正や決定といった行政処分を行うことができる期限のことを指しており、相続税法第36条に「贈与税についての更正、決定等の期間制限の特例」として規定されています。
ではこの「時効」、どの時点から数えて6年なのでしょうか?
この基準となる日を「起算日」といいますが、贈与税の申告期限が毎年3月15日なので、期限の翌日、つまり3月16日から数えることになります。注意してほしいのは、「贈与した日」ではなく「贈与した年の翌年3月16日」から数えるということです。あくまでも贈与「税」の時効なので、贈与税の申告期限が起算日となります。
令和5年7月27日に贈与をした場合の贈与税の時効は、令和5年分の贈与税の申告期限である令和6年3月16日から起算して6年後の令和12年3月15日、悪質であれば7年後の令和13年3月15日となります。
贈与税の時効が成立しない場合
ここまで読まれて、ホッと胸をなでおろした方、本当に大丈夫ですか?
実は贈与というのは、一方的に「これあげる」だけでは成立しないんですね。これについては民法第549条において次のように規定されています。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思 を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
つまり、贈与する側の「意思表示」と、贈与される側の「受諾」があって初めて贈与は成立します。
ここまで来るとピンとくる方もおられると思いますが、まさに「名義預金」などがこれに当てはまります。
例えば、おじいちゃんが保育園に通うお孫さんの名義で通帳を作り、1千万円の定期預金をしたとします。その通帳と印鑑はおじいちゃんが管理しており、お孫さんはその事実を認識しておりません。
この場合、この通帳の名義は形式的なものに過ぎず、実質的な名義はおじいちゃんであり、かつ保育園児であるお孫さんには、贈与の事実を聞かされたとしてもそれを正確に理解し受諾の意思表示ができるとは思えません。その後の通帳や印鑑の管理もおじいちゃんが行っていることから考えても、この贈与は成立していないと見るのが正解です。
つまり、そもそもの贈与契約が成立していない以上、贈与税の時効は成立しないことになります。
贈与税の申告漏れはバレるのか?
高確率でバレます。
まず、普段の確定申告や法定調書、国外財産調書、預金調査などから、高額な財産を所有している個人の情報や預貯金の動きを監視しています。株式などは年間取引報告書、生命保険などは生命保険金等の一時金の支払調書、暗号資産や先物取引に係る支払調書、NFTについても調書の提出、不動産の所有権移転情報の提供…
まだまだありますが、要は贈与した個人が黙っていても、金融機関や他の行政機関から自動的に情報が集まるような仕組みになっていますので、いまバレていないのは、「全くの偶然」だと思っておいたほうが良いでしょう。
とはいえ、贈与税の無申告が税務署にばれる一番のきっかけはやはり相続のタイミングでしょう。相続税の調査の際、相続に関わっている相続人等のすべての預金口座の動きを5年から7年間遡って細かくチェックしますので、過去に贈与があったかどうかは、ほぼこの時点で暴かれます。
税務調査でなくても、私達税理士は相続税の申告のお手伝いをする際、相続人等すべての預金口座の過去からの情報を細かく確認しますので、贈与税の無申告などが判明した場合、相続税の申告をする前に事前に対処します。
贈与税の申告漏れはバレないと高を括っておられる方もいらっしゃると思いますが、このように税務署がその気になればいとも簡単にバレてしまうものです。少しでも不安に感じる方は、すぐに税理士などに相談することをお勧めします。