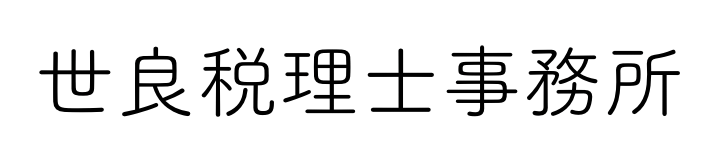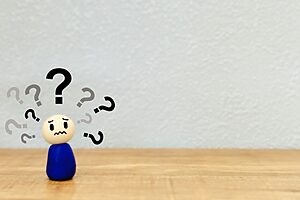通勤手当の処理は一見シンプルに見えますが、税務調査の現場では意外と否認される事例が多いことをご存知でしょうか?
本記事では、企業の経理担当者に向けて、通勤手当の正しい理解と、税務調査において否認されるリスクを限りなくゼロに近づけるための社内体制の構築方法を解説します。
通勤手当の基本:課税・非課税を正しく理解しよう
通勤手当の適切な処理は、法令を正しく理解することから始まります。特に経理実務では、単に金銭を支払うだけでなく、「通勤手当が税法上の非課税要件を満たしているか」を判断するための明確な根拠が必要です。まずは通勤手当と交通費の違いを理解し、非課税となるための要件を押さえましょう。
通勤手当と交通費の決定的な違いとは?
経理実務においては、「通勤手当」と「交通費」は性質が異なる費用として明確に区別されます。
交通費とは、従業員が業務遂行のために一時的、かつ都度発生する移動費用(出張費や得意先訪問のための電車代など)を指し、実費精算であれば原則として全額が非課税として扱われます。
一方、通勤手当は、従業員の自宅から勤務地までの通勤に対し、毎月または定期的に支給される手当であり、税法上の非課税限度額が設定されています。両者を混同すると、給与計算にも影響を及ぼすため、両者の違いを明確に理解しておくことが重要です。
非課税となる「通勤」の定義と、課税対象となるケース
税法上、非課税限度額内であっても、その通勤手当全体が給与と判断される、または不相当に高い部分について課税される可能性があります。
- 実質は基本給や残業代の一部であるにもかかわらず、「通勤手当」の名目で支給している場合
・・・この場合は全額が給与として課税されます。 - 通勤経路を虚偽申告している場合や、社会通念上不合理な経路・方法(不必要な遠回り、通勤に不要なグリーン料金など)を前提に非課税としている場合
・・・この場合は不合理な部分が課税対象となります。
経理担当者としては、単に申請された金額を支払うだけでなく、支給額の合理性を常に検証する必要があります。
通勤手当をめぐる最新の税制改正
マイカー通勤手当の非課税限度額:2025年度改正の具体的な影響と対応
マイカー通勤者の通勤手当に対する非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められていますが、令和7年11月20日に施行された改正により、同年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡及適用という形で、非課税限度額の引上げが決定・公布されています。
| 通勤距離【片道】 | 課税されない金額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 2㎞未満 | 全額課税 | 全額課税 |
| 2㎞以上10㎞未満 | 4,200円 | 4,200円 |
| 10㎞以上15㎞未満 | 7,100円 | 7,300円(+200円) |
| 15㎞以上25㎞未満 | 12,900円 | 13,500円(+600円) |
| 25㎞以上35㎞未満 | 18,700円 | 19,700円(+1,000円) |
| 35㎞以上45㎞未満 | 24,400円 | 25,900円(+1,500円) |
| 45㎞以上55㎞未満 | 28,000円 | 32,300円(+4,300円) |
| 55㎞以上 | 31,600円 | 38,700円(+7,100円) |
この改正により、令和7年4月以降の給与について、新しい限度額を適用して計算し直す必要があります。また、これらについては令和7年分の年末調整で対応することになりますが、発生する増差分を従業員へ還元するかは各社の判断となります。
定期券現物支給に関する取り扱い
定期券を現物支給するか、金銭で支給するかという支給形態そのものは、原則として課税・非課税の判断に影響しません。リスクとなるのは、支給内容が不合理・虚偽と評価されるケースです。
具体的には、定期券の区間や金額が「最も経済的かつ合理的な経路・方法」から逸脱している場合や、実際は通勤していない区間・家族の通勤に使われている場合などです。
したがって、現物支給を続ける場合は、通勤経路の申告内容を定期的に確認し、不合理な区間が含まれていないかチェックする体制づくりが重要です。
非課税限度額の判定をミスなく行うには?
通勤手当の課税リスクの多くは、「非課税限度額の判定ミス」に起因します。特に公共交通機関とマイカー通勤が混在している場合、計算は複雑になりがちです。この章では、具体的な支給申請があった際に、経理担当者が判断を誤らないための実務フローを3つの手順に分けて解説します。
手順1:交通手段に応じた非課税枠の上限金額を正確に把握する
非課税限度額は、交通手段によって明確に分けられており、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、1ヶ月あたり15万円が非課税限度額で、これは定期券代であっても同じです。
一方、マイカーやバイク・自転車などの交通用具を利用する場合、片道の通勤距離に応じて細かく限度額が設定されています。複数の交通手段を併用している場合は、それぞれの限度額を合算することが可能ですが、その前提として、合理的な通勤形態に即した実費相当額が上限となります。機械的な合算ではないため、最も経済的かつ合理的な一体の経路として判断することが、正確な処理のポイントです。
手順2:「最も経済的かつ合理的」な経路と運賃を裏付け資料で確認する
税法上の非課税要件である「最も経済的かつ合理的」な経路の確認は、経理担当者の重要な役割の一つです。単に運賃が最も安いだけでなく、通勤にかかる時間や距離なども考慮して、社会通念上妥当と認められる必要があります。
実務上の確認としては、従業員から提出された通勤経路図や運賃の証明書(定期券の領収書や購入履歴)に基づいて、オンラインの経路検索ツールなどを用いて、最短経路や最低運賃を検証することが求められます。もし申請された経路が明らかに遠回りであったり、不合理な特急料金を含んでいたりする場合は、合理的な経路の金額に修正するか、差額を課税処理する必要があります。裏付け資料の確実な保存も肝要です。
手順3:限度額超過時および自宅・勤務地変更時の課税処理を適切に行う
支給額が非課税限度額を超過した場合、超過した金額の全額を給与として扱い、所得税および住民税の課税対象とする必要があります。
この超過額は、社会保険料の算定基礎にも含まれるため、給与計算上のミスは許されません。また、従業員の自宅や勤務地が変更になった際は、原則として変更日以降の通勤手当について、速やかに非課税限度額の再計算を行う必要があります。特に、非課税限度額が変更になったにもかかわらず、従前の金額を継続して支給していると、過去に遡って否認されるリスクが発生します。変更の申請を受けたら、ただちに新しい経路と限度額を検証する体制が重要です。
税務調査で否認されないために社内体制を構築する
通勤手当に関する税務調査では、個々の従業員への支給額の妥当性だけでなく、「会社がどのようなルールで管理・運用しているか」という社内体制が厳しくチェックされます。経理担当者として、処理が正しいことを示すためには、きちんとした根拠と証跡が必要です。
この章では、税務署からの指摘を最小限に抑え、否認リスクを事前に排除するために、企業が整備すべき社内体制について解説します。
「通勤手当の定義と支給条件」を明記した旅費規程の整備と運用
税務調査において、通勤手当が非課税とされるためには、客観的かつ合理的な基準に基づいて支給されていることが必須条件です。そして、この基準を明確に定めたものが「旅費規程」や「通勤手当支給規程」です。
規程には、通勤手当の定義、支給の対象者、申請方法、非課税限度額の取り扱い、経路の選定基準、不正申告時の罰則などを具体的に記載しておく必要があります。規程がない、または内容が抽象的で曖昧な場合、支給そのものの合理性が疑われ、税務署に否認される可能性が高くなります。規程は作成するだけでなく、全従業員に周知し、規程通りに運用されている証拠を保持することも重要です。
虚偽申請を防止するための定期的な実態調査と記録
従業員が実際には定期券を購入していないにもかかわらず定期券代を申請したり、マイカー通勤距離を過大に申告したりする虚偽申請は、税務調査における否認の大きな要因となります。これを防ぐため、経理担当者は通勤手当の支給実態について、定期的な調査を実施する必要があります。
具体的には、定期券の現物提示を求める、マイカー通勤者に対して運転免許証や車検証のコピーを提出させる、オンラインの地図情報などで経路を再確認するなどの方法が有効です。これらの実態調査を行った日付と結果を記録として残すことで、企業として不正防止の努力を怠っていないことを税務署に明確に示すことができます。
駐車場代・高速道路代などの付随費用の課税・非課税判断基準の明確化
マイカー通勤に付随する費用のうち、有料道路料金は、その経路が「最も経済的かつ合理的な経路」に該当する場合には、通勤手当の非課税限度額に含めることができます。
一方、駐車場代については、従業員が個別に借りた駐車場の費用を会社が負担する場合は、一般的に給与として課税される取扱いが多く、会社が一括借上げした駐車場を通勤用として提供するようなケースでは、事情により非課税と認められる余地もあります。個別事情に応じて、税理士等と相談のうえ社内ルールを明確化しておくことが重要です。
【補足】令和8年以降に見込まれる制度変更の可能性
令和8年以降、通勤手当についてさらなる見直しが検討される可能性があります。人事院勧告などの検討案の一例として、マイカー通勤の新しい距離区分(例:65km〜100km超を5km刻み、上限66,400円)の新設や、駐車場などの付随費用について月額5,000円を上限とする非課税枠の新設が提案されています。
これらの内容は現時点で法令として確定したものではありませんが、今後、与党税制調査会などで調整が進む可能性があります。経理担当者としては、これらの「検討・調整中の案」についても動向を把握し、翌年以降の規定改定に備えておく姿勢が大切です。