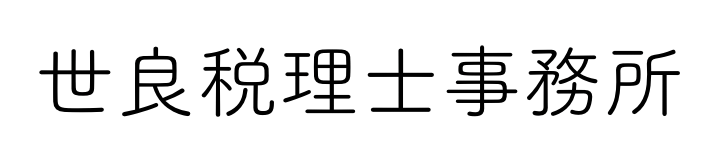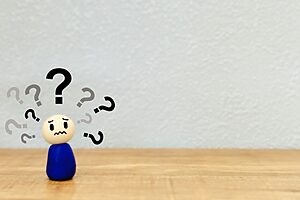社宅家賃はいくらに設定すれば否認されない?
前回は法人が社宅制度を導入することで福利厚生や節税面において有利になることを解説しましたが、今回は実際に社宅を運用するにあたって、役員や従業員から、家賃としていくら徴収すれば税務上問題がないのかについて見ていきたいと思います。
社宅家賃の具体的な計算方法については、国税庁のタックスアンサーに記載されており、その通りに計算した金額を家賃として受け取っていれば、役員や従業員の給与として課税されることはありません。
これだけではちょっと分かりづらいので、もう少し解説を加えて見てみましょう。
社宅が一般従業員向けのものである場合
実務上は、従業員本人の家賃負担額を法人が家主に対して支払う借り上げ賃料の50%以上に設定しておけば、税務署からまず否認されないため、これを賃料として採用するケースが多いですが、次に掲げる算式により「賃料相当額」を計算し、それを従業員負担分とした方が、殆どの場合、法人・従業員共に有利になります。
次の1~3の合計額が賃料相当額になります。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
- 12円 ×(その建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡)
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%
上記の計算をするためには、その社宅の賃貸借契約書と固定資産税評価額等証明書が必要です。
固定資産税評価額等証明書の取得または固定資産台帳の閲覧は不動産の所有者しかできないと思われがちですが、賃借人の立場であっても、市区町村役場に賃貸借契約書と本人確認書類を持参して申請することで、固定資産課税台帳の閲覧や証明書の取得が可能です。
もしも従業員に社宅を無償で貸与した場合、この賃料相当額が給与として課税されます。また、賃料相当額よりも少ない家賃を受け取っている場合には、両者の差額(賃料相当額 - 受け取っている家賃)が、給与として課税されます。
ただし、受け取っている家賃が「賃料相当額の50%以上」であれば、賃料相当額との差額については給与として課税されません。
この「賃料相当額の50%以上」というのは、冒頭の「法人が家主に支払う借り上げ賃料の50%以上」とは違う意味なので注意してください。
「法人が家主に支払う借り上げ賃料の50%以上」を採用するのは、賃料相当額を計算する際に必要な資料収集ができない場合や、単に計算が面倒くさい場合であって、殆どの場合はきちんと計算をしたほうが有利になると思ったほうが良いでしょう。
社宅が役員向けのものである場合
役員向けの社宅については、社宅建物の床面積によって役員が負担すべき家賃の金額が異なります。
小規模な住宅
「小規模な住宅」とは、次のいずれかに該当する建物をいいます。
・法定耐用年数30年以下の場合:132㎡以下
・法定耐用年数30年超の場合:99㎡以下
この条件に当てはまる社宅については、以下の計算方法により賃料相当額を計算します。
次の1~3の合計額が賃料相当額になります。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
- 12円 ×(その建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡)
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%
小規模な住宅でないもの
「小規模な住宅」の条件に合致しない建物がこれに該当します。
この場合の賃料相当額は以下の方法により計算します。
【自社所有の社宅の場合】
次の1と2の合計額の12分の1
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 12%
※法定耐用年数が30年超の建物の場合は10% - (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 6%
【借り上げ住宅の場合】
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額
豪華住宅
「豪華住宅」とは、社会通念上一般的でない規模の住宅のことをいいますが、具体的には以下のような基準により判定します。
- 240㎡超の場合:物件価格や賃貸料、内装および外装の状況などを勘案して判定
- 240㎡以下の場合:プールやジム、サウナ等の設備や役員の個人的嗜好の反映度により判定
役員に貸与する社宅が豪華住宅に該当する場合、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額となるため、社宅制度のメリットがなくなってしまうことに注意しましょう。
最後に
今回は適正な賃料相当額について役員と従業員の場合に分けて考えましたが、次回は最終回として、社内規程の整備や社宅制度を活用した具体的な節税について見ていきたいと思います。